新しい農業資材「バイオスティミュラント」って何? 肥料や農薬との違いを解説
2019/10/23

2019年7月、日本バイオスティミュラント協議会による第2回講演会が行われた。最近にわかに聞かれるようになった「バイオスティミュラント」とは一体何なのか、日本でどのように普及しているのか、講演会で語られた内容から説明しよう。
バイオスティミュラントとは?
「バイオスティミュラント(Bio stimulants)」…直訳して「生体刺激資材」は、植物に対する非生物的ストレスを制御することにより気候や土壌のコンディションに起因する植物のダメージを軽減し、健全な植物を提供する新しい技術だ。
食料を安定生産するために、人類は、優秀な作物遺伝子資源の開発=育種を筆頭に、病害虫から植物を守る農薬、植物の栄養となる肥料、土壌の性質を変化させて農業生産に役立てる土壌改良材、といった技術を進化させてきた。バイオスティミュラントは、この何処の範疇にも収まらない新しい農業資材である。
●バイオスティミュラントと農薬の違い
バイオスティミュラント=非生物的ストレスを緩和する

農薬=生物的ストレスを緩和する

●バイオスティミュラントと肥料の違い
バイオスティミュラント=植物栄養素の取り込みを高める
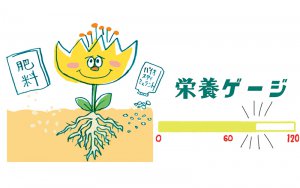
肥料=植物に栄養を供給する

●バイオスティミュラントと土壌改良材の違い
バイオスティミュラント=植物をより良い生理状態にする

土壌改良材=土壌を物理的・化学的・生物的に変化させる

ここまで読んでもピンと来ない方も少なくないだろうが……バイオスティミュラントは日本でも古くから使われていた。米糠や油粕などの植物質を発酵させて施用する、いわゆる”ぼかし肥料“がソレである。
ぼかし肥料は直接的に植物の栄養とはならないが、それを使うことで根が強くなったり、不良環境への耐性が高くなる、といったメリットが生まれる。これは一つのバイオスティミュラントと呼んで良く、現在もぼかし肥料からヒントを得た農業資材が市販されている。
バイオスティミュラントの役割

作物は遺伝的に、種の時点で収穫時の最大収穫量が決まっている。ところが、発芽時や、苗の時期、開花期、結実期、収穫直前などに、病気や害虫(生物的ストレス)、高温や低温、物理的な被害(非生物的ストレス)により、本来、収穫できるはずだった収量が減少して行く。このうちの「非生物的ストレス」による収量減少を軽減することが、バイオスティミュラントの役割である。
発芽期から収穫に至るあらゆる過程で様々なストレスが存在するため、それに対応するために下記のように多種多様なバイオスティミュラントが開発されている。
●バイオスティミュラントの原料と、様々な作用(一例)
| 種類 | 作用 | 腐植質・有機酸 | 海藻・多糖類 | アミノ酸・ペプチド | ミネラル・ビタミン | 微生物 (生菌) |
植物/ 微生物抽出物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向上・促進系 | ①ストレス耐性 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ②代謝向上 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ③光合成促進 | ◯ | ◯ | |||||
| ④開花・着果促進 | ◯ | ◯ | |||||
| 調整・コントロール系 | ⑤蒸散調整 | ◯ | ◯ | ||||
| ⑥浸透圧調整 | ◯ | ◯ | |||||
| 根の賦活系 | ⑦根圏環境改善 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ⑧根量増加/根の活性向上 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ⑨ミネラルの可溶化 | ◯ | ◯ | ◯ |
引用:高木篤史 2019年度 日本生物工学会北日本支部 仙台シンポジウムより
バイオスティミュラントの本場
ヨーロッパの現状
日本ではまだ馴染みが薄いバイオスティミュラントであるが、視野を世界に広げると、全く異なる様相を呈している。
バイオスティミュラントの世界市場は2014年に1400億円に達しており、2021年には2900億円に拡大すると言われている。その先頭を行くのがヨーロッパ(EU)であり、ここ数年の年間成長率は10-12%で推移している。その背景には、自然素材や食品の廃棄物を有効活利用したり、減農薬栽培を試みるなどの社会背景も一因となっていると考えられる。
一方で、EUにおいてもバイオスティミュラントの標準化・規格化はなされていないが、2022年5月から施行される新肥料法にはバイオスティミュラントや微生物資材についても包括的に記載され、施行後はCE※マークをつけることが可能となる。これによりヨーロッパに市場では、より一層バイオスティミュラント市場の成長が期待されている。
※CEマーク:商品がすべてのEU (欧州連合) 加盟国の基準を満たすものに付けられる基準適合マーク。
日本でも協議会の発足で
規格化を目指す
最後に、日本におけるバイオスティミュラントを取り巻く状況をご紹介しておく。
日本におけるバイオスティミュラントの標準化・規格化に向けて、2018年1月に日本バイオスティミュラント協議会が発足。同協議会にはアリスタライフサイエンスやハイポネックスといった、バイオスティミュラントを扱う企業などで構成され、2019年8月現在では、正会員19社、賛助会員38社が参加している。
同協議会では、欧米の法制調査や国内農業資材規格の現状把握を行い、また行政(担当省庁)との対話を行っている。目標とするのは、現行の農業資材(農薬・肥料等)と同等のバイオスティミュラントの規格化である。
日本バイオスティミュラント協議会HP
バイオスティミュラントは法的に規定されていない現状だが、実質的にはバイオスティミュラントとして機能する製品が、肥料取締法や地力増進法に基づいて、肥料や土壌改良剤として適正に販売されている。
今後、標準化・規格化が進むことで、バイオスティミュラントの機能・効果はもちろん、品質や安全性が広く認知されれば、生産者にとって身近な存在になって行くはずである。
問い合わせ
Text:Reggy Kawashima
Illustration:Hiroshi Kawai
AGRI JOURNAL vol.13(2019年秋号)より転載













