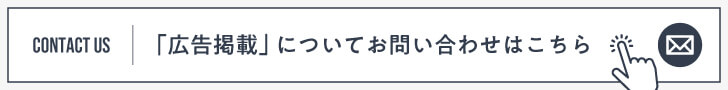株間の雑草も高確率で除去! 有機農家の“救世主”、オーレックの「WEED MAN」
2020/08/24

「除草作業における負担を軽減し、安全・安心な食づくりに取り組む方々を支援したい」という理念を掲げる、オーレックが打ち出した渾身の除草機「WEED MAN」。今回は、試作段階から当製品を愛用している有機農家、遠藤竜史さんに使い心地などを伺った。
WEED MANの
使い心地は?
「健康と自然に配慮した、安心・安全な米を作りたい」という思いのもと、家族で有機栽培に取り組む遠藤竜史さん。現在取り入れている栽培方法の土台は、遠藤さんの父親の弘人さんがつくりあげたそう。なお、その栽培方法は少々ユニークだ。
「肥料として、完熟発酵した鶏ふんに加え、隣町で産出される貝化石を使っています。ミネラルが多分に含まれている貝化石には、米の食味に“キレ”をもたらす効果が期待できます」。

遠藤さんが管理する、約1.2haの圃場。WEED MANを購入した2018年6月に撮影。
化学肥料はもちろん、除草剤をはじめとする農薬を使っていないため、“田植え後は、しぶとい雑草との戦い”。過去には、人手を集め、手作業で延々と雑草を抜き取ることが多々あったという。長年にわたり、除草作業は重労働として遠藤さん一家にのしかかっていたが、およそ6年前、オーレックの除草機に出会ったことがいい転機に。遠藤さんは、こう振り返る。

圃場に生える雑草のオモダカ。丈夫な根をもち、稲の養分を収奪してしまう。
「オーレックと、当時はまだ試作機だった『WEED MAN』を紹介してくれたのは、私たちと同じように有機栽培に取り組む、九州在住の農家さんです。以降、改良にも携わりながら『WEED MAN』を使用しています。
ちなみに、試作機の使用中は、『条間だけでなく、株間も除草できたらいいですね』といったアドバイスをさせてもらいました。こうした希望も反映された『WEED MAN』を使い始めてから、除草作業がとても楽になりましたね。圃場の状態と『WEED MAN』の相性が良ければ、除草率は90%以上にもなります」。
“農薬に頼らなくても米作りはできる”と話す、遠藤さん。そんな心意気を後押しするのが、「WEED MAN」なのだ。

株間の雑草を絡め取り、除去する「回転レーキ」

コントロールパネル上に操作系のレバーや調整ダイヤルなどがあり、操作しやすい。
PROFILE
遠藤竜史さん
1982年、福島県白河市生まれ。父の弘人さんが始めた有機栽培での米作りを、高校在学中から手伝う。他業界での勤務を経て、2006年に就農。現在、家族で運営する「遠藤有機農園」の社長を務める。
DATA
業界初となる除草機構「回転レーキ」と「除草刃ローター」を備え、条間のみならず、株間の除草も実現した点が最大の特長。機体前方に作業機が配置されており、作業状況を目視で確認できるため、確実な除草が叶う。
希望小売価格(税別):
SJ600(6条) ¥3,850,000
SJ800(8条) ¥3,950,000
問い合わせ
株式会社オーレック
TEL:0943-32-5002
写真・文:緒方佳子
AGRI JOURNAL vol.16(2020年夏号)より転載
Sponsored by 株式会社オーレック