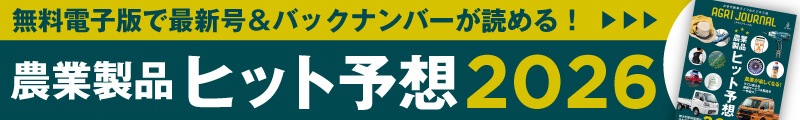「未来型大規模水田作モデル」の運営農家が語る、スマート農業の成果と米づくりの“これから“
2025/10/24

スマート農業の普及が進んでおり、その注目度も年々、高まっている。今回は、福井県の南西部にある若狭地域にて、スマート農業を大々的に展開する「株式会社若狭の恵」を取材。スマート農業を始めたきっかけから、近年の米価に対する見解まで、幅広くお話いただいた。
黒字経営を目指し
スマート農業に挑戦
株式会社若狭の恵の代表を務める前野恭慶さんが、若狭地域で本格的に米づくりをするようになったのは、2004年頃のこと。当時から、高齢化や担い手不足などが課題となっており、地域の稲作農家は危機的な状況に置かれていたが、その後、米農家を取り巻く状況は、さらに厳しくなったという。こう、前野さんは説明する。
「今から10年くらい前のことです。米価が下がるいっぽうで資材の価格が上がったため、米を作っても赤字にしかならなくなってしまいました。一反分の米を作ると、2〜3万円の赤字が出ていました」。
 液体肥料の散布などができるドローン。若狭の恵では、ドローンを使った作業の代行業も展開している。
液体肥料の散布などができるドローン。若狭の恵では、ドローンを使った作業の代行業も展開している。
財務状況を赤字から黒字に変える方法の一つが、田んぼの大規模化とスマート農業の導入だ。広大な田んぼを確保し、一反分の田んぼにかける作業時間を短縮することで、収益を出すことが可能になる。
こうした算段のもと、前野さんをはじめとする地域の農業者が寄り集まり、2015年7月に大規模農業法人「株式会社若狭の恵」を設立。同社の代表取締役には、前野さんが就任した。同社は、設立の翌年である2016年には、担い手への農地集積と集約化を促進する「農地中間管理事業」を活かし、約120haの田んぼを確保。この広大な田んぼを適切に管理して収量をあげるため、先端技術を活用したスマート農業に取り組み始めた。
実証プロジェクトへの参加が
飛躍的な成長のきっかけに
若狭の恵が“スマート農業の先進農場”として飛躍的に成長したのは、2019年のこと。農林水産省が展開するスマート農業の実証プロジェクトである「中山間地域におけるデータをフル活用した未来型大規模水田作モデルの実証」に、若狭の恵が採択されたのだ。これを機に、国から研究費や補助金が支給されたため、若狭の恵はロボットトラクタ、自動運転田植機、食味収量測定コンバインなど、先端技術が搭載された機器を導入した。
 苗を等間隔で植えつけ、肥料も適切に散布する自動運転田植機。GPS機能により、田んぼの形状に合わせた田植えが可能だ。
苗を等間隔で植えつけ、肥料も適切に散布する自動運転田植機。GPS機能により、田んぼの形状に合わせた田植えが可能だ。
前野さんいわく、実証プロジェクトが始まってから間もなくして、明らかな成果が得られたという。まず、10aあたりの米の収量は、平均して9.7%増加。加えて、品質(食味スコア)も可視化できるように。コシヒカリを栽培する圃場のおよそ4割で、80点以上の食味スコアが確認できたため、“おいしさ”を具体的にアピールできるようになった。さらには、作業時間の削減にも成功。10aあたりの作業時間が平均52.5%カットされたそう。
若狭の恵での実証プロジェクトは2021年3月に終了したが、以降も同社は、各種スマート農機を活用し続けた。その結果、同社は国内でも有数の「未来型大規模水田作モデル」として注目を集めるように。同社の圃場や設備を見学するため、毎月2〜3組の視察団がやってくるほか、代表の前野さんが講師として登壇し、自社の取り組みを紹介する機会もたびたびあるという。
■未来型大規模水田作モデル
自動運転田植機や農業用ドローンなど先端技術が搭載された農機や、効率的な営農を可能にするアプリなどを活用し、大規模な水田で耕作する農業経営体。面積あたりの労働時間の削減と、高い収益性の確立を目指す。担い手不足などが課題となっている現在、本モデルの重要度が高まっている。
また、福井県では、ドローンや自動運転田植機といったスマート農機を導入する農家が増加した。これは、若狭の恵が実証プロジェクトに取り組んだことも影響している。同社はスマート農機を導入するにあたり、当時は県内にほとんどなかったRTK基地局を自社の敷地に設置。
その後、実証プロジェクトが進み、県内でスマート農業に対する関心が高まったことなどを受け、福井県側が複数のRTK基地局を新設している。こうしてスマート農機を導入しやすい環境が整い、これが県内で導入事例が増えるきっかけとなった。
研究機関との連携で
プロジェクト参加を勝ち取る
 若狭の恵は、乾燥調整場も所有。本機を使うことで、米を出荷するまでの作業内容が詳細に記録される。こうした機能などを活用し、同社はJGAPを取得。
若狭の恵は、乾燥調整場も所有。本機を使うことで、米を出荷するまでの作業内容が詳細に記録される。こうした機能などを活用し、同社はJGAPを取得。
人手不足に悩んでいる農業生産者のなかには、すぐにでもスマート農業に取り組みたい人もいるだろう。前野さんによると、スマート農業に移行するうえで役立つアクションの一つが、大学との連携だという。
「弊社では実証プロジェクトに応募するにあたり、京都大学と東京大学にコンタクトをとり、実証プロジェクトでの連携を打診しました。その結果、京都大学でロボティクスを教える教授や、東京大学の農業経営学研究室に所属する教授から協力を得られることになりました」。
なお、スマート農業実証プロジェクトの推進チームが公開している資料を見ると、農業生産者と研究機関などが連携し、本プロジェクトに取り組むことが推進されている。スマート農業実証プロジェクトのような公的なプロジェクトでの選考時は、研究機関などとの連携が可能かどうかが、ポイントとなりそうだ。
また、前野さんいわく、従業員のスマート農機への順応力も、スマート農業への転換時は重要になるという。
「弊社には、スマホに馴染んでいる20〜30代の社員が多いです。スマート農機を動かす時はスマホやタブレットから指示を出すので、そうしたデバイスを使いこなせるというのは、大きな利点に。スマート農機の扱い方もすぐに覚えてくれたので、結果的に、スマート農機を円滑に現場に導入できました」。
米価が上昇し
やっと収支が合うように
世間では、米価の上昇が注目のトピックとなっている。約30年間、米づくりに携わり、米や稲作に関する動向を見つめ続けてきた前野さんに、このトピックへの見解もお話いただいた。
「ニュースなどでは『米価が高騰している』と報道されていますが、正直、こうした伝え方には違和感を抱いています。高騰しているのではなく、『やっと採算がとれる価格になった』というのが、こちらが抱いている感覚です」。
このように感じる背景には、これまで米農家が直面してきた苦境がある。トラクターなど米づくりに必要な機械の価格は、年々、大きく値上がりしてきた。さらには肥料など、資材の価格も上昇。それにも関わらず米価は低迷していたため、経営面の収支が合わない状態が続いていた。
「それでも先祖代々受け継がれてきた田んぼを守るために、そして地域のために農業をやってきました。赤字を補填するために借金をしながら、稲作をしている農家も珍しくありません」と、前野さん。しかし近年、米価が上がったことで、やっと採算がとれるようになったという。
 高活性腐食酸を配合した液状複合肥料、穀物の健やかな成長をサポートする菌根菌を原料とするバイオスティミュラントなど、新しい資材も積極的に使用している。
高活性腐食酸を配合した液状複合肥料、穀物の健やかな成長をサポートする菌根菌を原料とするバイオスティミュラントなど、新しい資材も積極的に使用している。
経営面だけでなく、栽培面での苦労もある。夏場の異常なほどの高温をはじめ、米の健やかな成長を妨げる要因は多い。こうした厳しい状況下で稲作を続けていくためには、どのような心がけが必要だろう?
「これまでの栽培方法を続けていると、米がうまく育たず、経営面にも影響が出てくる可能性が高い。栽培品種を高温に強いものに切り替える、新しい資材を導入する、といったアクションが必要でしょう。その分、経費は増えるかもしれませんが、それは必要経費と捉え、積極的に新しい方法に挑戦したほうがいいと思います」。
取材協力
株式会社若狭の恵
前野恭慶(やすのり)さん

株式会社若狭の恵の代表。株式会社若狭の恵は、農作物の生産・加工・販売などを行う農業法人。現在は、約150haの農地で米と、ミディトマトをはじめとする野菜を生産している。米の栽培品種は、コシヒカリ、つきあかり、アキサカリなど。特別栽培米や、ひまわりを漉き込んだ土壌で栽培する「ひまわり米」も、当社の自慢の商品だ。
写真・文/緒方よしこ