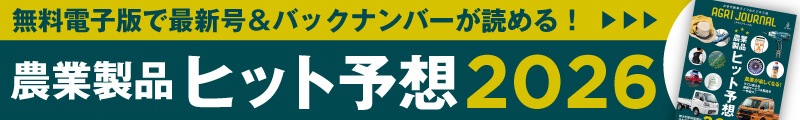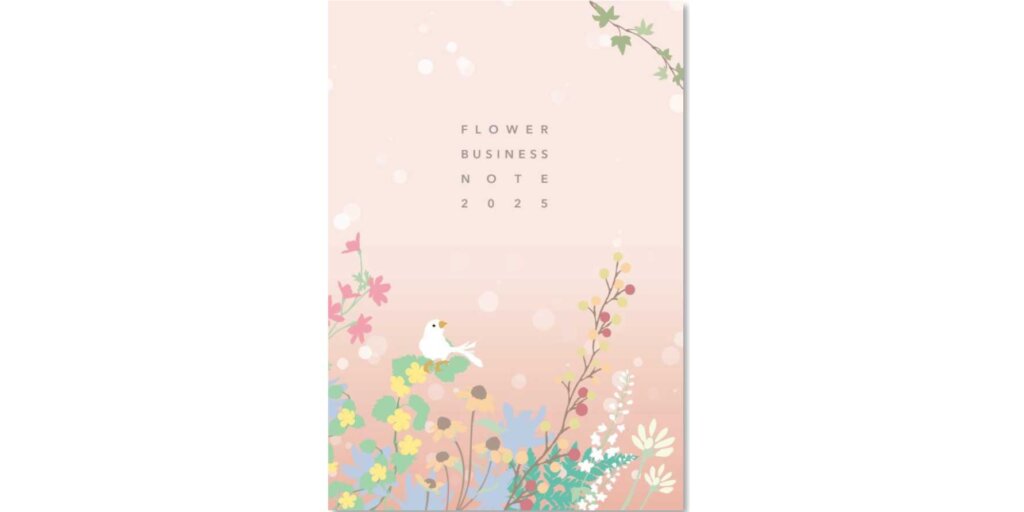花き生産に新たな動き! 「枝物」が躍進、メイン品目以外の「1・2年草」がメガヒットを記録
2024.12.23

「2027年国際園芸博覧会」の開催が近づいてきた。花博を前にした今、日本の花き産業は、どのような状況なのだろう? 「フラワービジネスノート」の発行元として知られる、株式会社大田花き花の生活研究所に聞いた。
メイン画像提供:株式会社大田花き花の生活研究所
大田花き花の生活研究所は
花きのシンクタンク

東京都中央卸売市場大田市場は、全国14の中央卸売市場のなかで、花きの取り扱い高で日本一を誇る。2024年1月現在、花き卸売業者は2社、仲卸業者は20店舗・17業者、売買参加者は1,391人にのぼる。
東京都中央卸売市場大田市場 花き部門の卸売業者2社のうちの1社が株式会社大田花きである。お話をうかがった大田花き花の生活研究所(以下、花研)は、大田花きの子会社に当たる。
大田花きは全国一の花き卸売会社だ。取扱量、品種ともに日本で最も多く、そのため花きに関する膨大な取引データが日々積み重なっている。子会社である花研は大田花きの取引データをビッグデータ化し統計的な分析などを行って、花き産業に還元している。
また、統計データのみならず社会トレンドについても研究を行い、花き業界のファッショントレンドの分析情報の提供、未来トレンド予測などの発信も行う。
こうした成果の一部は、花き業界唯一の専門情報冊子「フラワービジネスノート」として取りまとめて毎年発行している。行政民間問わず個別のコンサルティング・調査依頼にも応じるほか、地域団体向けの講演なども行うことで花き業界の情報共有を進めている。
縮小傾向にある花き生産だが
躍進している品目もある
2022年産では、日本の農業総産出額は約9兆円だが、花き産出額はそのうちの3,493億円(3.9%)という市場規模である。
花研の代表取締役を務める桐生進さんによると、花き生産現場も農業生産現場と似た状況にあり、同じような課題に苦しめられている。花き生産数の高齢化と減少の同時進行、資材・燃料費の高騰、夏場の酷暑などである。

花き市場の動向について、桐生さんが説明してくれた。
「これらの影響を受けて、国内の切花出荷量はこの27年間、平均すると1年で1億本ものペースで減少し続けています。2023年の出荷量は、ピークであった1996年の約53%と、半分近くにまで減少しているのです。
花き産出額の内訳をみますと、切花類がもっとも多く55.5%。これに鉢物類の27.0%、花き苗類の9.2%、花木類(ツツジやマツなど根巻きの花木類のこと)の4.9%が続きます。
切花では、冠婚葬祭とお墓参り・仏壇などに幅広く使われるキクが39.2%でトップですが、次にシェア6.9%で切枝(枝物)が第2位に入ってきたのが近年のトピックです」
枝物とは、簡単にいえば、樹木の枝。昔から生け花では四季折々の枝物が、また季節催事では桃の枝がひな祭りで飾られていた。近年は、四季の移り変わりを楽しめる枝物を手軽に自宅で飾る需要が高まり人気が出ているという。
施設栽培は野菜から転向できる。
今注目は露地栽培!

農業メディアへの対応として、桐生さんは花き生産と農業生産の関係性も説明してくれた。
「歴史的にみれば、1970~1990年代ごろまでは花き生産面積が増加していました。新規に花き生産を始める方もいれば他の品目から転向される方もいて、その一部は施設野菜生産者の転向によるものでした。例えばピーマンからスイートピーへといった具合です。ところがバブル崩壊後の景気低迷とともに、また一部の方は野菜に戻ってしまいました。
影響としては限定的でしょうが、これが花き産出額が1996年ピークから減少している原因の1つでしょう。また、この頃から日本社会全体の可処分所得が減少し続け、世帯あたりの花き消費支出もそれまでの右肩上がりから踊り場になったという状況です。
先ほどご説明したように、花き生産と野菜生産のどちらかを選択するという競合関係にある場合もありますし、ハウス栽培の設備でしたら花きと野菜両方での利用が可能なので、シーズンで作るものを変えるという場合もあります」
 大田花きが主催する「フラワー・オブ・ザ・イヤーOTA」で表彰された枝物 「ミモザアカシア」。
大田花きが主催する「フラワー・オブ・ザ・イヤーOTA」で表彰された枝物 「ミモザアカシア」。
先に桐生さんは「枝物のマーケットが伸びている」と説明してくれたが、これには花き生産者側にとってのメリットが多いことが見逃せない、という。
「枝物に強いニーズがあるという前提のもとの話ですが、枝物生産には、ハウス栽培に無いメリットがあるんですよ。
枝物栽培はほとんどの場合露地で行いますから、圧倒的にランニングコストが低い。これは資材・燃料価格が高騰している今、大きなメリットです。また、枝物は必ずしも開花した花の有無を問いません。季節のグリーンとしての楽しみ方があるからです。そのため収穫遅れを気にすることなく栽培できることも大きなメリットです。人手の確保が難しい昨今ですが、深夜から早朝の収穫・出荷作業を必要としないような枝物商品を選択すれば、収穫期の自由度が大きいのです」
 道端や公園などに生えている「ナズナ」がメガヒットを記録している。(写真提供:株式会社大田花き花の生活研究所)
道端や公園などに生えている「ナズナ」がメガヒットを記録している。(写真提供:株式会社大田花き花の生活研究所)
また、同じく「ニーズがある」という前提のもとに、それまでは大きく注目されることがなかった1・2年草が、メガヒットを記録しているという。
「それは例えば日本中あちこちの道端で見かける『ナズナ』です。この植物を露地やハウスで生産出荷している花き生産者さんがいるくらいなんですよ。
これには、自然風や田舎風であることを愛でるファッショントレンドが背景にあり、その流れを受けて、例母の日に贈るブーケなどに『ナズナ』が使われるようになったことを見越した動きです」
桐生さんは取材中、幾度も「トレンドを先読みして、需要があるものを生産することが大切」と繰り返していた。野菜生産よりも、この点に関してはシビアなのだろう。
同研究所が発行している冊子「フラワービジネスノート」には、花き産業のトレンド分析や展望が書かれているから、ご興味を持たれた方は手に取ると良いだろう。
~花研式!世界でただひとつの業界展望ツール~
今後の農業生産や花き流通業界は、価値向上に向けた変革が求められています。 特に、コスト高が続いており、国内の切花出荷量は減少しており、2023年には1996年の半分近くまで落ち込んでいます。生産減少やコスト上昇、気候変動などは個人ではコントロールできなくとも、適応可能な場合があります。たとえば、草花や枝物を中心とした露地栽培の拡大がその一例です。生産、消費でも枝物が注目されている現状を受け、本書では枝物の取引動向を読み取っていただけるよう、枝物にフォーカスして情報を集めました。
今後、花き産業は大きく構造が変わると予想され、業界関係者が共に情報を共有し、進化していくことが重要です。
ぜひ、本書にて現在の花き業界の現状を把握するとともに、業界における変化を読み取っていただき、益々魅力ある産業として成長できますようご活用いただけると幸いです。
「フラワービジネスノート2025」4つのポイント
1.【最新】花き業界基礎データ集&社会経済の統計情報
2.【特別企画】世界で唯一の枝物分析マップ
3.【月別】流通早見表 全350品目 枝物品目はさらに充実
4.【推し消費を押さえる】生活者マインドを先読みした販売アイデア 48例
<商品規格>
サイズ A5(210mm×148mm)
厚さ 6mm
全128ページ(メモページ以外は全ページフルカラー)
マンスリーカレンダー 2024年10月~2026年3月(たっぷり18か月分!)
本文に環境負荷の少ない「水なし印刷」を採用しています。
HP:フラワービジネスノート
文/川島礼二郎
RANKING
MAGAZINE
PRESS