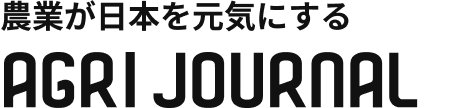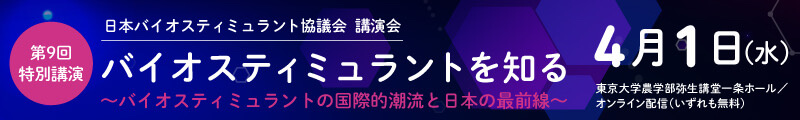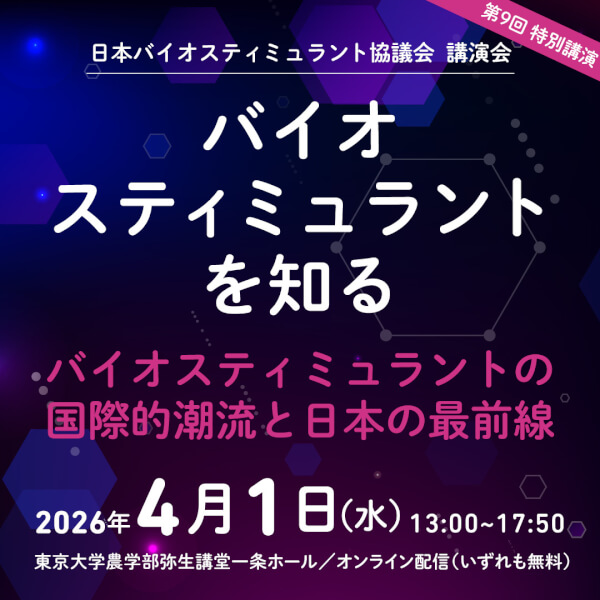【菌根菌(きんこんきん)】とは?活用方法や増やし方を解説!
2025.08.12

菌根菌は作物の栽培において、栄養吸収の効率化や土壌の改善など、多くのメリットをもたらす有益な菌である。本記事では、菌根菌の種類や特徴、効果的な活用方法、土壌の最適化について詳しく解説する。農業生産への活用を検討している方は必見だ。
1.菌根菌(きんこんきん)とは? 外生菌根菌、内生菌根菌について解説
2.菌根菌が植物と共生することのメリット・デメリット
3.菌根菌の活用方法について
4.米ぬかと菌根菌による相乗効果
5.まとめ
作物の栽培に良い影響を与えることで知られる菌根菌(きんこんきん)は、農業の生産現場で有効に活用されている成分として知られている。
菌根菌は土の中で上手く増やせば、効率的な栄養素の吸収や肥料、水の節約、土壌の改善などさまざまな効果をもたらす。
ただ、菌根菌をどのように活用したら良いのかについて頭を悩ませている方は少なくない。
そこで今回は、菌根菌の活用方法と増やし方を解説する。
菌根菌(きんこんきん)とは?
外生菌根菌、内生菌根菌について解説

菌根菌とは、植物の根に共生している糸状菌のことをいう。
陸上に生息している8割の植物は菌根菌と共生していて、植物とともに養分を供給しあって助け合う特徴があり、上手く利用すれば肥料を与えなくても栽培が可能になる。
そして菌根菌には、一般的に2つの種類がある。
・外生菌根菌
・内生菌根菌
菌根菌の特徴について詳しく解説していく。
外生菌根菌
外生菌根菌とはマツ科やブナ科、フタバカキ科の樹木の根に共生する菌根菌で、キノコを形成する菌として知られている。
野菜や果物とは共生できないが、林業分野で重要視されている。
中でもマツタケは外生菌根菌によって形成されていて、マツ科やブナ科の木と樹木の根を通じて地下で結びついて地面に生えてくることから、生育には重要な存在だ。
内生菌根菌
内生菌根菌は、宿主植物の細胞の内部にある菌根菌のことだ。
内生菌根菌は以下の5つの種類がある。
・エリコイド菌根菌
・アーブトイド菌根菌
・モノトロボイド菌根菌
・ラン菌根菌
・アーバスキュラー菌根菌
これら5つの菌根菌の大きな違いは、共生している植物が異なることだ。
エリコイドとアーブトイド、モノトロボイドは主にツツジ科の植物と共生し、ラン菌根菌はその名の通りラン科の植物と共生する。
上記4つの菌根菌は特定の植物としか共生しないが、アーバスキュラー菌根菌(VA菌根菌)は被子植物や裸子植物など、多くの植物と共生している。
アーバスキュラー菌根菌は、古くから地球上に存在した菌根菌の1つで、土壌の栄養素を根から吸い取るには欠かせない菌とされている。
菌根菌が植物と共生することの
メリット・デメリット
菌根菌が植物と共生するメリットは、水や養分の吸収が促進されて病気や害虫への抵抗力を強くしてくれる点だ。
菌根菌には土壌にある栄養素を植物に効率良く運ぶ特徴があり、農家にとっても収穫量の増加や品質の向上を手助けしてくれる貴重な存在だ。
しかし有効態リン酸の含有率が高い土壌や、リン酸が多い化学肥料を使用した土壌においては、効果が薄くなってしまう。
他にもダイコンなどのアブラナ科、ホウレンソウに代表されるヒユ科の植物に関しては、一般的に菌根菌が共生しない。
菌根菌の活用方法について

菌根菌は、適用するタイミングや良い土壌条件が整えば、農業生産で有効に活用できる。
しかし、どのように活用するべきか悩んでいる方は多いのではないだろうか?
ここからは、菌根菌の活用方法を解説していく。
適切な菌根菌資材の検討
適切な菌根菌資材を選ぶには、作物が育つ環境や作物の種類、土壌の状態などさまざまな条件について検討する必要がある。
植物の種類によって適切な菌根菌は大きく異なるため、それぞれの植物に合った適切な菌根菌資材を探してみよう。
他にも土壌の相性の良さや、生存繁殖が可能であるかどうかも見極める必要がある。
もし長期間にわたって菌根菌資材を使用するなら、環境への影響や持続可能かどうかを確認する必要もあるので、必ずそれぞれの目的に合ったものを選ぶようにしたい。
適用タイミングと方法
菌根菌を適用するタイミングは、育苗中や定植直前の時期が最適だ。
おすすめの菌根金資材は育苗中に2,000倍に水に希釈し灌水して使う水和タイプで、定植直前にドブ付けしよう。
この他にも健康な表層土をポット用土に混ぜたり、苗床の中にあらかじめ菌根菌が形成された松の苗木や稚樹を植え込んだりするのも効果的だ。
菌根菌を適用する方法はさまざまなので、それぞれの植物に適した方法を選ぶようにしよう。
土壌条件の最適化
菌根菌が住みやすい土壌条件を作る方法は、土壌中のリン酸量を減らして炭化材を含むのが最適だ。
アーバスキュラー菌根菌は、リン酸が多い土壌では活動しないため、植物と共生できない。
そのために必要なのが炭化材を含ませることで、炭化材には胞子を増殖させる効果がある。
菌根菌に有効な炭化材は木炭や竹炭、もみ殻燻炭など、アルカリ性のバイオ炭だ。
土壌中のリン酸量を少し減らす方法
菌根菌を活かすには、土壌中のリン酸量を少しでも減らす必要がある。
リン酸量を減らすには、堆肥や腐植酸資材を使うのが最も効果的だ。
堆肥や腐植酸資材が土壌中のリン酸を囲んで、土壌コロイドとの接触を少なくできる。
ストレス条件下での活用
菌根菌は、干ばつや洪水、塩分、酸性土壌といったストレス条件下でも植物の生長を支えてくれる。
菌根菌は、植物の根と共生し土壌にある養分などを吸収して、周辺にある植物に養分を提供する。
これにより、植物は水の吸収が促進されて乾燥に対する耐性が強化され、ミネラルの吸収も促進される。
病気や害虫の攻撃に対して強くなり、どんな気候でも強い耐性を持つため、菌根菌は植物が長く生き残る上で大切な要素の1つだ。
実際に高ストレスの環境下では、多くの菌根菌が生息している。
こうしたことから、菌根菌は農業生産において重要な存在だ。
米ぬかと菌根菌による
相乗効果
菌根菌と米ぬかは、一緒に活用することによって強い相乗効果を得られる。
米ぬかにはミネラルやビタミンが豊富に含まれていて、菌根菌の増加に効果的だ。

主な相乗効果は、以下の3つ。
・栄養の豊富さによる生長の促進
・土壌改良効果
・病害虫対策
これらの相乗効果に関して、詳しく解説していこう。
1.栄養の豊富さによる生長の促進
米ぬかを使用して菌根菌を増殖させることで、植物の栄養も増殖し生長を促進する。
短い期間で生長させるだけでなく、根を強く根付かせ、土を活性化させることができる。
栄養が豊富になることで、植物はより丈夫に育つ。
あるネギ農家では、菌根菌を使用して生育を促進した成功例がある。
アーバスキュラー菌根菌を含んだ資材を散布しただけで、生育スピードが高まり、生産性を向上させることに成功した。
このように、菌根菌は農作物の生産性を高める手助けをしてくれる。
これらの成功例に関して詳しく知りたいと思ったら、こちらの記事を参考にしてみると良いだろう。
2.土壌改良効果
菌根菌を有効に活用するには、効果的な土壌改良が必要になる。
菌根菌を使用する際には、事前にそれぞれの土壌に合わせた菌根菌資材を使用しなければ、十分な効果は得られない。
土壌には、物理的な条件や排水性、通気性などさまざまなことを配慮する必要がある。
菌根菌を上手く活かすためにも、事前の土壌分析は妥協しないようにしよう。
3.病害虫対策
菌根菌は、病気や害虫からの攻撃に対して強い植物を育てることから、病害虫対策に効果的だ。
菌根菌は水の吸収を促進させる効果があり、ミネラルが吸収されて土壌の構造が強くなるメリットがある。
病害虫対策の注意点は、仮に病害虫を発見したとしても、殺虫剤などを使用するのを避けることだ。
殺虫剤の使用は菌根菌に対して逆効果であり、かえって作物が害虫の攻撃に弱くなってしまうためだ。
まとめ

今回は、丈夫な作物を育てるために重要な菌根菌の活用方法や増やし方を解説した。
菌根菌は丈夫な作物を育てる上で欠かすことのできないものとなっている。
また干ばつや洪水など、ストレス条件下に強いのも菌根菌の大きな特徴だ。
このように菌根菌は持続可能な農業生産を実現する大切な存在でもあるので、ぜひ作物を育てる時に有効に活用してみよう。
監修:山門昭雪
Xアカウント:@yasaidaisuki6
野菜と多肉のぴー農園園主 幼いころから祖母の畑で遊び、国立T大学農学部卒。種苗会社で育種、産地開発、園芸相談などを担当。土壌医。
RANKING
MAGAZINE
PRESS