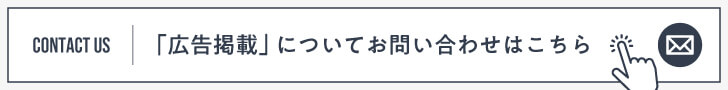農産物流通をスマート化する『スマートフードチェーン』とは
2021/08/20

スマート農業ではサプライチェーンの下流をも巻き込んだ展開が顕著だ。ここでは「スマートフードチェーン」「スマート・オコメ・チェーン」について、その構築に携わる流通経済研究所の折笠氏による解説を聞いた。
食品流通における
データ活用の現状
いま、食品流通においては、加工食品などを中心にほとんどの商品がロット番号で履歴管理をされている。ペットボトル飲料も良く見るとキャップの下に数字と英字のロット番号が入っていることがわかるだろう。このロット番号を使えば、万が一、何かあった場合に、どのような原材料で、いつ、どこの工場で生産された商品であるかをすぐに特定し、回収などをスムーズに行うことができる。
しかし、農産物や水産物といった生鮮食品では法律で決められている牛肉などの品目を除き、ロット管理などはほとんどされていない。それは、工場で生産されているわけではないので、ロット番号のラベルを貼り付けたり、管理したりすることが難しかったからだ。
その一方で、農水産物の生産現場では、スマート農業の取り組みも含め、IT化が進んできており、生産管理ソフトを使った生産履歴の管理も普及してきている。
ここに実は大きな問題がある。畑や水田などの生産の現場のデジタル化が進み、せっかく生産にかかわる様々なデータを取得していても、結局、ロット番号などが生産した農産物に入っていないために、その生産履歴と農産物は出荷してしまった後には結びつかないのである。さらには、苦労して取得した生産現場のデータが、出荷したあとのデータ(流通先の販売履歴や消費者の口コミなどを含む)にも一切結びつかないのである。
ある程度のカタマリ(=ロット)単位でも、農産物(商品)を特定できなければ、生産履歴データと商品を紐づけすることができないためだ。
データ連携だけではない
スマートフードチェーン構築
この問題を解決するためのプロジェクトがスマートフードチェーン構築事業である。生産から流通、消費までのフードバリューチェーンにおいて、農産物等を出荷箱単位で情報管理するために、各段階のデータを連携させるデータ連携基盤(システム)を構築する事業だ。
これは、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの一環として実施されている。
ここで伝えたいことは、スマートフードチェーンは、生産に係わるデータと流通・販売に係わるデータを単に結び付けるだけのものではなく、データの連携を通じて、バリューチェーンの付加価値向上につなげることを目指す取り組み、ということである。
▶▶▶『戦略的イノベーション創造プログラム』について詳しく知る
例えば、スマートフードチェーンの構築によって、以下のようなことが可能になる。
①事務処理の作業効率化
生産者と流通がデータ連携することで、手書き伝票を無くした取引が可能となり、伝票処理などが非常に楽になる(EDI化)。
②スマートフードチェーンとの連携による情報提供
どのような生産管理ソフトを使っていても、そのソフトがスマートフードチェーンと連携していれば、生産履歴などを複数の顧客に簡単に送信できる(顧客ごとにシステム対応の必要がなくなる)。
③トレーサビリティの簡易化
ロット番号単位、あるいはシリアル番号単位で流通の履歴を管理することができるため、トレーサビリティ管理が容易にできる。
④品質管理のデータ化
商品の流通の記録として取り扱いの温度情報や衝撃情報を記録することで、流通段階の取り扱いも含めた品質管理ができる。
⑤生産者と消費者をつなぐ
産地や生産者の情報をサプライチェーンの下流である小売業や消費者に伝えられるようになる(=新しい販売促進や訴求が可能となる)。例えば、QRコードからスマートフードチェーンにアクセスして、商品情報や産地情報を取得できるようにするなど。
⑥商品開発・発展におけるデータ活用
小売業の販売履歴データや、消費者の購買履歴データなどを生産者や種苗会社が取得することで、新しい品種開発や、播種時期の選定などに活用できる。
他にも、データ連携によって、生産予測や消費予測、あるいはそれらを組み合わせた需給マッチングなども可能になることが見込まれる。つまるところ、分断されていた生産と流通、消費をデータでつなぎ、それぞれのフェーズの生産性の向上や高付加価値化を目的にしている。このスマートフードチェーンは、2023年度の社会実装(システム本稼働)を目指している。
「スマート・オコメ・チェーン」
コンソーシアムの役割
そして、2021年度6月から「スマート・オコメ・チェーン」がスタートした。生産から消費に至るまでの情報を連携し、生産の高度化や販売における付加価値向上、流通最適化等による農業者の所得向上を可能とする基盤(スマートフードチェーン)を米の分野で構築するというプロジェクトである。
お米は、日本人の主食であり、国内農業の中核であり、文化的な面からも、安全保障の面からも重要な農産物である。国内における米消費・米需要の減少と海外輸出への期待を含め、今こそ、コメ流通のイノベーションが求められていることが、このプロジェクトの背景にある。
これは、農水省が主管し、有志から成る「スマート・オコメ・チェーンコンソーシアム」という組織が中心となって推進するものであり、その中では、国際標準化を視野に入れた海外調査や、国際ワークショップの開催、現場実証などを通じたスマート・オコメ・チェーンの検討を行うことを予定している。
スマート・オコメ・チェーンは、コメ流通のDX化とも言えるものであり、以下のような未来を実現するためのものである。
①生産履歴データ、検査データ、流通データを連携して、コメのトレーサビリティ管理が可能になる
②輸出先国に合わせた検査結果データや、産地証明書等の電子発行によるコメ輸出の加速に貢献
③新しい米の規格制定(新しいJAS規格の制定や民間規格の制定にデータを活用)

こちらについては、試行錯誤しながら、業界全体で検討し、推進していくものとなっている。コンソーシアムメンバーの募集やシンポジウムなども開催予定であるため、興味のある方は参加をいただけると幸甚である。
まさに今、コロナ禍の影響やデジタル化の急速な発展を背景として、青果だけではなく、コメも流通の大変革期であるといえる。新たな変革のなかでは、生産者、卸、小売、飲食業などのステークホルダー全体の連携と協調が重要になるだろう。
▶▶▶『スマート・オコメ・チェーンコンソーシアム』について詳しく知る
筆者プロフィール
公益財団法人 流通経済研究所
主席研究員 折笠俊輔氏

小売業の購買履歴データ分析、農産物の流通・マーケティング、地域ブランド、買物困難者対策、地域流通、食を通じた地域活性化といった領域を中心に、理論と現場の両方の視点から研究活動・コンサルティングに従事。日本農業経営大学校 非常勤講師(マーケティング・営業戦略)。