政策・マーケット

鈴木農林水産大臣は1月20日の記者会見で、2027年度からの水田政策の見直しについて「できるだけ6月中に詳細を示すことができるよう検討を進めたい」と述べた。
鈴木農相 1月20日記者会見「水田政策見直しの詳細を6月中に示すよう検討を進めたい」

鈴木農林水産大臣は1月9日の記者会見で、主食用米の価格高騰が米粉の供給に影響を及ぼしているとして、「水田政策の見直しのなかで、米粉の安定供給につながる施策を確立していきたい」と述べた。
鈴木農相 1月9日記者会見「水田政策の見直しのなかで、米粉の安定供給につながる施策を確立」

政府は昨年12月26日、2026年度政府予算案を閣議決定した。農林水産関係では、米の安定生産に向けて、高温耐性のある種子供給や節水型乾田直播の導入支援などに約15億円を計上した。
【2026年度政府予算案】米の安定生産へ 高温耐性の種子供給や節水型乾田直播の導入支援などに15億円を計上
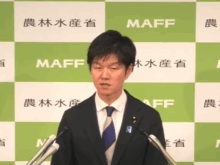
鈴木農林水産大臣は12月26日の記者会見で、高市政権が進める成長戦略の策定に向けて、フードテックWGにおいては、植物工場、陸上養殖、食品機械、新規食品の4分野のユニットを設け、2026年春頃までに検討結果を取りまとめる考えを示した。
鈴木農相 12月26日記者会見「植物工場、陸上養殖、食品機械、新規食品の4分野で成長戦略の検討結果を2026年春頃までに取りまとめ」

鈴木農林水産大臣は12月23日の記者会見で、 米の所得補償制度について「初めからたくさんつくって、米価がどんと下がった場合に所得補償するという立場は取り得ない」と述べた。
鈴木農相 12月23日記者会見「米を増産して下落時に所得補償するという立場は取り得ない」

施設園芸やハウス栽培には、初期投資や設備更新、燃料費など多額のコストがかかる。国では今年度も補助制度が用意されており、これらを活用することで経営基盤を強化できる。本記事では主要な補助金制度をわかりやすく解説する。今年度の申請をすでに締め切っている補助金もあるが、2026年度の事前準備として把握しておこう。
【2026年度】施設園芸・ハウス栽培で活用できる補助金ガイド

日本最大の産直通販サイト「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデンは、全国の生産者に対し、クマやイノシシなどによる鳥獣被害の影響について、生産現場での実態調査を実施。東北・信越地方を中心に被害の拡大を実感する生産者が増える一方、自治体支援が不足する現状がみえてきた。
【調査】クマなどの鳥獣被害が拡大し9割の生産者に影響。自治体支援は約半数にとどまる

農林水産省と農研機構は、スマート農業技術の活用促進を目的に「スマート農業推進フォーラム」を全国9ヶ所で開催する。会場では、最先端テクノロジーを搭載した農機具などの展示が行われる。参加は無料だが、事前の申し込みが必要だ。
全国9ヶ所でスマート農業推進フォーラムを開催 最先端の農機具を展示

農林水産省は、来年2月からの事業開始を希望される方を対象として、2025年度第3回目の「雇用就農資金」の募集を10月21日から開始した。今年度から1経営体あたりの新規採択人数は5人を上限とし、3人目以降の支給を減額する。
【雇用就農資金】10月21日から第3回目の募集開始!新規就農を支援する農業法人、1経営体あたりの上限は5人

農家の人手不足や、安定した就業場所の減少による人口流出など、地方の抱える課題の改善策として注目を集める「特定地域づくり事業協同組合制度」。この記事では制度の仕組みから、認定要件、事業の始め方までわかりやすく解説する。










