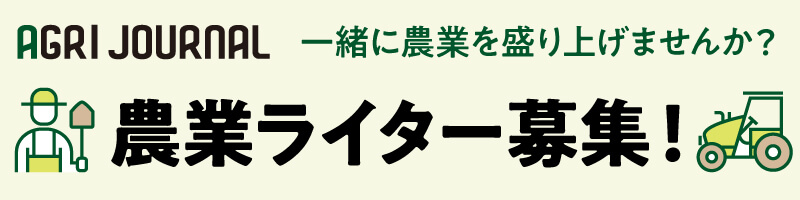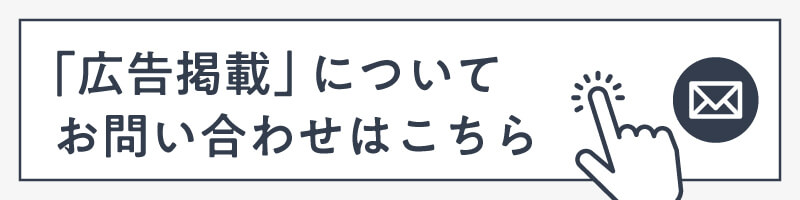神門教授が説く現代農業の本質「日本の漆職人から学ぶべきこと」とは?
2018.05.09

明治学院大学経済学部の神門教授によるコラム、「現代農業の本質」。今回のテーマは「漆器を使おう」。神門さんが考える、漆関連の職人から学ぶべきこととは?
木の食器に漆を塗ると長持ちするようになる。だから普段使いにいい。漆の塗りたての真新しい色つやも、使い込まれて褪せた色も、それぞれに楽しい。また、漆の塗り直しをしてさらに使うこともできる。
会津は古くから漆器の産地として有名だ。一般に伝統工芸の職人というと、気難しくて求道的なイメージを持たれがちだが、会津の漆関連の職人は、総じて、あっけらかんとしていて気持ちよい。
会津では古くから漆がよく植えられていたし、食器の材料に適した種類の木にも恵まれていた。会津の経済力が強く、職人たちを集めやすかった。会津は内陸で重量物の出荷には不利だが、食器類のような小物の漆器ならばその問題がない。
いまの会津の漆関係の職人は三代目が多い。つまり、百年近く前に創業したことになる。そのころは、第一次世界大戦を契機に重工業が勃興し、農村から都市へと、日本国内で大規模な労働移動があった。都会に住み始めた人々が、日用品として漆器を買い揃えたため、会津の漆産業が活気づいたのだ。
漆関連の職人には、材木を食器の形状に彫り込む木地師、漆を薄く層状に木の表面に塗る塗師、漆の層の上に絵を描く蒔絵師、などがある。もちろん訓練を積み、技能を習得しなくてはならないのはどの職人でも同じだ。だが、普段使いの日用品を作る場合は、宝物のような高級品に比べれば、ストレスは少ない。たまの失敗は仕方ないとして、おおらかに構えることができるからだ。
蒔絵師、塗師、木地師と、最終製品から遠くなるほど、その傾向が強い。さらに、木地師の職場は、開放的だし木からの芳香に包まれていて爽快だ。
考えてみると、「天才バカボン」のパパも植木職人だ。そういう等身大の職人が身近にいてこそ、社会の精神構造が豊かになる。
戦後、プラスティックなどの新素材に圧されて漆器が日常生活から減り、芸術品のジャンルに入れられがちになった。しかし、リーズナブルな値段で、食洗器で洗える手軽な漆器もある。漆器がもっと使われて、食卓と社会に温かみが増えてほしい。
プロフィール
神門善久さん
明治学院大学 経済学部経済学科教授
1962年島根県松江市生まれ。滋賀県立短期大学助手などを経て2006年より明治学院大学教授。著書に『日本農業への正しい絶望法』(新潮社、2012年)など。
『AGRI JOURNAL』vol.7より転載
RANKING
MAGAZINE
PRESS