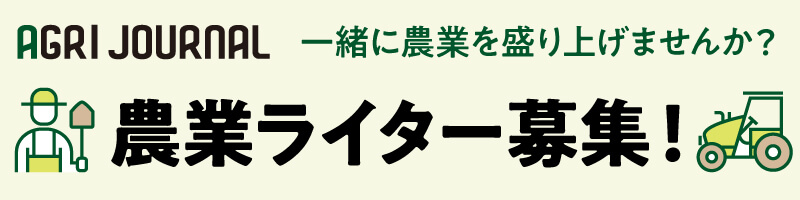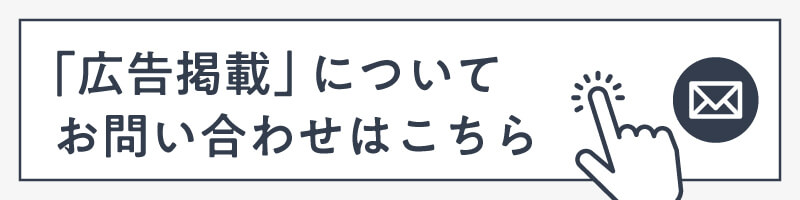第二次世界大戦後の雑草管理史から学ぶ。 地球温暖化の歯止めに農業が注目される理由
2020/03/12

第二次大戦後の世界農業は効率化への道を歩んだ。草生栽培の基礎を教えてくれた伊藤先生に、雑草管理の世界史について解説していただいた。
化学薬剤の導入と
生物多様性の消失
牛馬や人力を中心とした労働集約型の日本農業を変えたのはGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)でした。日本農業に科学薬剤、配合化学肥料、内燃機関原動機、養鶏、養豚技術と配合飼料が持ち込まれたのです(注:もちろんタダというわけではありません)。
この中で化学薬剤は、有害生物(害虫・雑草・病原菌・ネズミ)を撲滅する武器(兵器)という西洋科学概念とともに導入されました。手にした殺虫剤、除草剤、殺菌剤、殺鼠剤と呼ばれる化学薬剤の効果は驚くべきものでした。以後、官民一体となって開発普及に向かうことになります。
本家となる欧米では、工業資材多投入による単一作物の大規模栽培が進み、単位収量が飛躍的に伸びていきます。そこで起こったことは、レイチェル・カーソン氏の『沈黙の春』がベストセラーになったことに象徴されるように、自然環境への化学物質の残留・蓄積や地下水の汚染などによって生物多様性が失われるという警告でした。
英国でも国土の3/4を占める農地において生物の多様性が失われたことが大問題となりました。欧米の農業界に深刻な問題として提示されたのは、このまま現在の農法を続ければ表土の有機物は枯渇し、生物多様性はおろか生態系サービスも失われ、農業の持続が困難になることです。
遺伝子組み換え大豆の出現
そこでアメリカでは、農地の土壌有機物の消耗と土壌流亡を防ぐ壮大なプロジェクト「LISA」(Low Input Sustainable Agriculture:低投入で持続可能な農業)を推進します。これが不耕起栽培法(土壌を耕さないで表土に有機炭素を保全する農法)と呼ばれるもので、このために開発されたのが除草剤抵抗性作物(遺伝子組み換え大豆など)なのです。
英国もまた「FSE」(Farm Scale Evaluation)と呼ぶ壮大な試みから除草剤抵抗性作物の導入を検討しました。これは農地の生物多様性への間接的影響を評価することが目的でした。詳しいことは省きますが、この結果から、英国は農地を文化遺産としてその生物多様性を保全することにしたのです。
こうして欧米では、雑草管理は農業生産者だけの問題ではなく、表土と生態系保全や文化継承とも密接に関係したものである、という考え方が広がっていきました。
農業と地球温暖化の関係
こうした方向性は、近年さらに加速しています。2016年に発行されたパリ協定では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」「できる限り早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と森林をはじめあらゆる緑地資源を強化し、吸収量のバランスをとる」と定められています。この二酸化炭素排出量を減らすという点で、農業が脚光を浴びているのです。
地球上に土壌有機物として存在する炭素は表層(表土)40cmの範囲だけで1550ギガトン。これに土壌無機物として存在する950ギガトンを合わせると、2500ギガトンになります。なんと、地球温暖化の原因とされている大気中の炭素の(800ギガトン)の3倍以上、植物として存在する炭素(560ギガトン)の4.5倍に相当するのです。
言い換えれば、土壌は巨大な二酸化炭素の倉庫なのです。より多くの炭素を農地に貯めることができれば、大気の二酸化炭素濃度を下げることができる。つまり、温暖化に歯止めがかけられる。そのうえ、農業生産において有限の資源である表土の有機物を大切に扱うことは、低炭素・低投入で持続可能な農業につながるのです。
PROFILE
伊藤幹二さん(農学博士)

特定非営利活動法人緑地雑草科学研究所 理事/マイクロフォレストリサーチ株式会社 代表取締役社長。京都大学大学院で果樹園芸学を学び、イーライリリー社、ダウ・アグロサイエンス社に勤務し、広く世界の農業・園芸分野で植物の育成・保護技術の開発と普及に携わった。草の管理と土壌の関係を誰よりも広く深く知る、この道のエキスパートだ。
text:Reijiro Kawashima
AGRI JOURNAL vol.14(2020年冬号)より転載