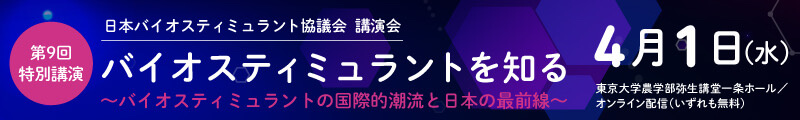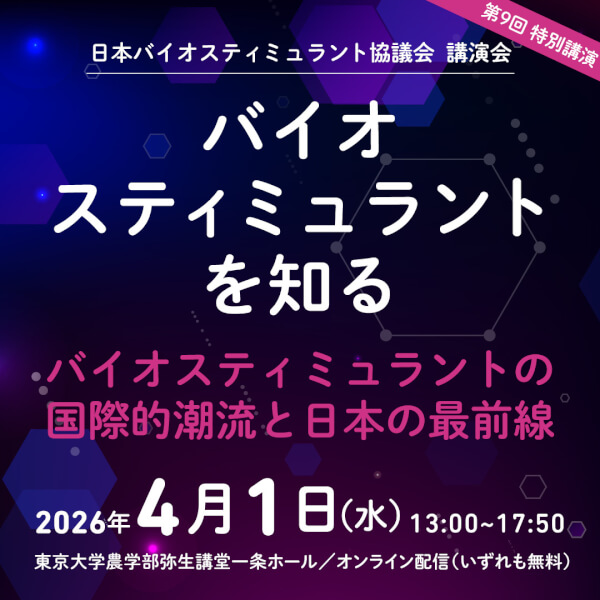政策・マーケット
アフターコロナで農業はどうなる? 外国人労働力だよりの農業、終焉へ
新型コロナウイルスの問題は農業にどんな影響を与えるのだろうか。アフターコロナの農業とJAの在り方を考える、中央大学教授の杉浦宣彦氏による連載コラム第2回。
コロナは農業をどう変えた? 4Hクラブが各地の農家へ影響調査
全国農業⻘年クラブ連結協議会では、20〜30 代前半の農業者へアンケートを4月に実施し「新型コロナウイルス感染症の影響」を調べた。調査によると、出荷数減となったのは60%以上で、今後の不安要素は「取引先の減少」が多いことが分かった。キャッシュ不⾜による資⾦難や、離農への⼼配の声もあがっている。
異業種3社が業務連携をして推す「agri-board(アグリボード)」とは?
IT ベンチャー「株式会社はれると」に、農業用ハウス・資材メーカーの「イノチオグループ」とシステム開発企業「株式会社カオナビ」が出資し、業務連携をスタート。その期待される効果とは?
アフターコロナで農業はどうなる? 人々の農業観に変化はあったのか
非常事態宣言下で人々の農業観に変化があったのだろうか。また、新型コロナウイルスの問題は農業にどんな影響を与えるのだろうか。アフターコロナの農業とJAの在り方を考える、中央大学教授の杉浦宣彦氏による連載コラム。
最新アグリビジネスの成功の秘訣は? 先進事例から学ぶ講演レポート
近年の規制緩和や消費者の安心・安全志向の高まり、さらにはコロナ不安すらも追い風にして、今アグリビジネスへの注目が高まっている。ここでは、そんなアグリビジネスにおける先進事例から成功の秘訣を学ぶことができる研究会を紹介しよう。
川の氾濫や水質悪化は高原レタス栽培の代償か? 連作障害が引き起こすものとは
一年前、長野盆地で起きた千曲川の氾濫。新幹線車両センターが水没するなど甚大な人的・物的被害を生んだ。この原因が、高原レタス栽培にある可能性があるのだ。現代農業の本質を問う、神門善久氏のコラム。
ハチの減少を食い止め保護に繋げる! 世界中に住処を増やすオープンソースプロジェクト
現在、世界全体で2万種以上のハチが生息している。ところが、近年の気候や農業環境などにより、個体数が減少している。そんなハチたちを守り、より多くの生態系をグローバル規模で保護しようという試みがスウェーデンで行われている。
亀岡盆地の京野菜生産が危機に直面! 原因は「投機目的での農地所有」の蔓延にあった
明治学院大学経済学部の神門教授によるコラム、「現代農業の本質」。今回のテーマは「京野菜生産の危機」。なぜ伝統料理に不可欠な食材がなぜ危機に直面してしまったのだろうか。原因は投機目的での農地所有が蔓延していることにあると指摘する。
【視察・講演会】自社の成長に何が必要かを知る! ビジネスモデル再構築のためのポイント
農業参入後の黒字化や、さらなる事業拡大には、何が必要となるのだろうか? 幅広い領域でコンサルティングを行うタナベ経営による「アグリビジネスモデル研究会」で学べる、ポイントの一部を紹介しよう。
農業プラットフォームと葉色解析サービスがタッグ! 農家間での情報交換の場を提供開始
農業プラットフォーム「agmiru」は、葉色解析サービス「いろは」と連携して「agmiru×IROHA」の提供を開始した。画像の解析結果についてユーザー間の意見・情報交換ができる場になる他、解析結果をもとに必要な資材を購入することも可能だ。
RANKING
MAGAZINE
PRESS